I. 身体的拘束最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は患者様の自由を制限するのみならず、身体的・精神的な弊害をもたらすため、当院では緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束をしない診療・看護の提供に努めます。
<身体的拘束の定義>
「衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を制限する行動の制限をいう」(昭和63年4月8日 厚生省告示 第129号における身体拘束の定義)
<身体的拘束の対象となる具体的な行為>
<身体的拘束の定義>
「衣類または綿入り帯等を使用して一時的に該当患者の身体を拘束し、その運動を制限する行動の制限をいう」(昭和63年4月8日 厚生省告示 第129号における身体拘束の定義)
<身体的拘束の対象となる具体的な行為>
- ① 徘徊しないように、車いすやいす、べッドに体幹や四肢をひもで縛る。
- ② 転落しないように、べッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
- ④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- ⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- ⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- ⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
- ⑧ 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- ⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、べッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- ⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
- ⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
Ⅱ.身体的拘束最小化のための体制
身体的拘束最小化のため、専任の医師及び専任の看護師、薬剤師、理学療法士、事務職員からなる身体的拘束最小化チームを設置します。身体的拘束最小化チームは、定期的に身体的拘束の実施状況を把握し、医療安全委員会へ報告することで職員への周知徹底を行います。また、定期的に身体的拘束最小化に関する研修を開催し、当指針の見直し及び職員への周知を行います。
Ⅲ.身体的拘束最小化に取り組む姿勢
身体的拘束をせずにケアを行うために、下記の3つの原則に取り組みます。
<身体的拘束をせずに行うケアの3つの原則>
<身体的拘束をせずに行うケアの3つの原則>
- 身体拘束を誘発する原因を探り、除去する。
- 5つの基本的ケアを徹底する。
※5つの基本的ケアとは、①起きる、②食べる、③排泄する、④清潔にする、⑤活動する(アクティビティ)という5つの基本的事項についてのケアのことである。 - 身体拘束廃止をきっかけに「よりよいケア」の実現に取り組む。
Ⅳ.緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合の対応
例外的に緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合、下記の3要件をすべて満たす状態であることを確認し、医師を中心とした複数の医療者で慎重に判断を行います。また、緊急やむを得ず身体的拘束を行った場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録した上、解除することを目標に鋭意検討を行います。
<緊急やむを得ない場合に該当する要件>
(「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議)より抜粋)
<緊急やむを得ない場合に該当する要件>
【切迫性】
利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
【非代替性】
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
【一時性】
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
Ⅴ.鎮静を目的とした薬物の適正使用
不眠時や不穏時の薬剤指示については、患者様の病状や既往症などに合わせて担当医師が適宜判断して対応します。
Ⅵ.本指針の閲覧
本指針は当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、患者様やご家族が閲覧できるようにホームページへ掲載します。
令和6年12月1日策定
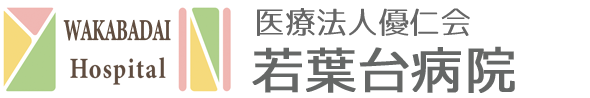
Be the first to comment